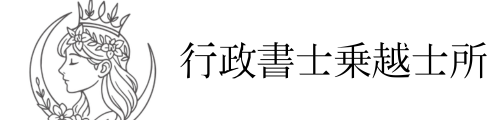(令和7年10月26日一部改正)
第1章 総則
(目的)
第1条 本規則は、乗越士所における事務の処理に必要な文書等(電磁的記録を含む。私書、図画、印刷物等の当事務所の事務処理に関しないものは除く)の形式及び管理について定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規則は、当事務所内で作成・取得・発出されるすべての文書等に適用する。ただし、儀礼上発行する文書、案内文書、その他管理を適当としない文書については適用しないことができる。
第2章 文書等の定義
(文書等の定義)
第3条 この規則において「文書等」とは、当事務所が職務上作成し、又は取得した文書及び図画等をいう。
(文書等の区分)
第4条 文書等は、次に掲げるところにより区分する。
一 一般職務文書 当事務所の日常業務の処理、報告、連絡、会議資料等の作成を目的とする文書
二 特定職務文書 規則等の定め又はその規定に基づき、権限を有する者が職務上作成し、又は発出する文書
第3章 特定職務文書の区分
(特定職務文書の区分)
第5条 特定職務文書は、次の各号に分類する。
一 公告・告示等 規則等の定めに基づき、一定の事項を公式に広く一般に知らせるために作成し発出する文書
二 命令 当事務所が発令する命令をいい、次の区分に分類する。
イ 一般命令
ロ 特別命令
ハ 個別命令
ニ 日々命令
三 部課局命令 部課局が発する命令で、その権限が部課局長に属するものをいう。次の区分に分類する。
イ 部課局長一般命令
ロ 部課局長特別命令
ハ 個別命令
ニ 職務等命令
ホ 日々命令
四 通達 当事務所が発出した訓令を文書化したもの
五 部課局達 各部課局がその任務又は所掌事務の処理のために発出した訓令を文書化したもの
六 その他特定職務文書等 前各号に掲げるもののほか、事務所の運営上必要な特定職務文書をいう
第4章 文書の構成及び文書管理番号
(文書番号の付与)
第6条 当事務所が発行する文書には、文書管理番号を付与するものとする。
2 文書管理番号は、次の要素によって構成することを常例とする。
一 発行元符号
二 文書区分番号
三 元号年
四 発行通番号
3 前項第二号について、必要に応じ、文書区分番号に副区分を設けることができる。
(文書管理番号の付与の特例)
第7条 第6条の規定にかかわらず、次の書類については文書管理番号の一部又は全部を省略できる。
一 請求書、領収書、見積書 前条第2項第二号についてのみ省略
二 送付状、お礼状、営業用文書、社会通念上番号付与が相当でない書類 全部省略
(文書の構成)
第8条 文書等は、その文書等の性質に照らして、許されないときを除き、次に掲げる項目をもって構成する。ただし、文書等の性質に照らして適当でないと認めるときは、この限りではない。
一 文書管理番号
二 発行年月日
三 宛先(受信者名・所属等)
四 発行者(事務所名・所在地・担当者等)
五 文書名
六 本 文
七 付記(備考・添付資料等)
(職印の押印)
第9条 文書等には、事務所長の職印を押印しなければならない。ただし一般職務文書に関して、事務所長が定めるときは、この限りではない。
(職印の省略)
第10条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない場合は職印を省略できる。
2 省略する場合、文書管理番号上部に「(代表者職印省略)」と表示すること。
第5章 文書等の保存・管理
(保存方法)
第11条 文書等は、原則として電磁的記録によって保存する。ただし、必要に応じて書面等の形式によって保存することができる。
(保存期間)
第12条 文書等は、原則として7年間保存するものとする。ただし、他の規則等によって、個別に定めることができる。
(廃棄)
第13条 保存期間経過後の文書等は、事務所長の承認を得て廃棄する。
第6章 文書作成・送付の留意事項
(作成上の留意点)
第14条 文書等の作成にあたっては、内容の正確性、客観性、礼節、可読性を重視し、業界の標準及び社会通念並びに慣習等を尊重して作成しなければならない。
第7章 補則
(他の規則等との関係)
第15条 行政書士業務に関する書類や資料等の保管は、別に定める。
(この規則の改廃)
第16条 この規則の改廃は、事務所長の承認を得て行う。
第8章 附則
(施行)
第1条 本規則は、令和7年10月12日から施行する。
2 本規則の改正は、事務所長の承認を得て行う
令和7年10月26日改正
(施行)
第1条 この規則は、令和7年10月26日から施行する。